Initiativesくうねあの取り組み
「くすの木の魅力って何?」を保護者ライターさんと語り合ってみました
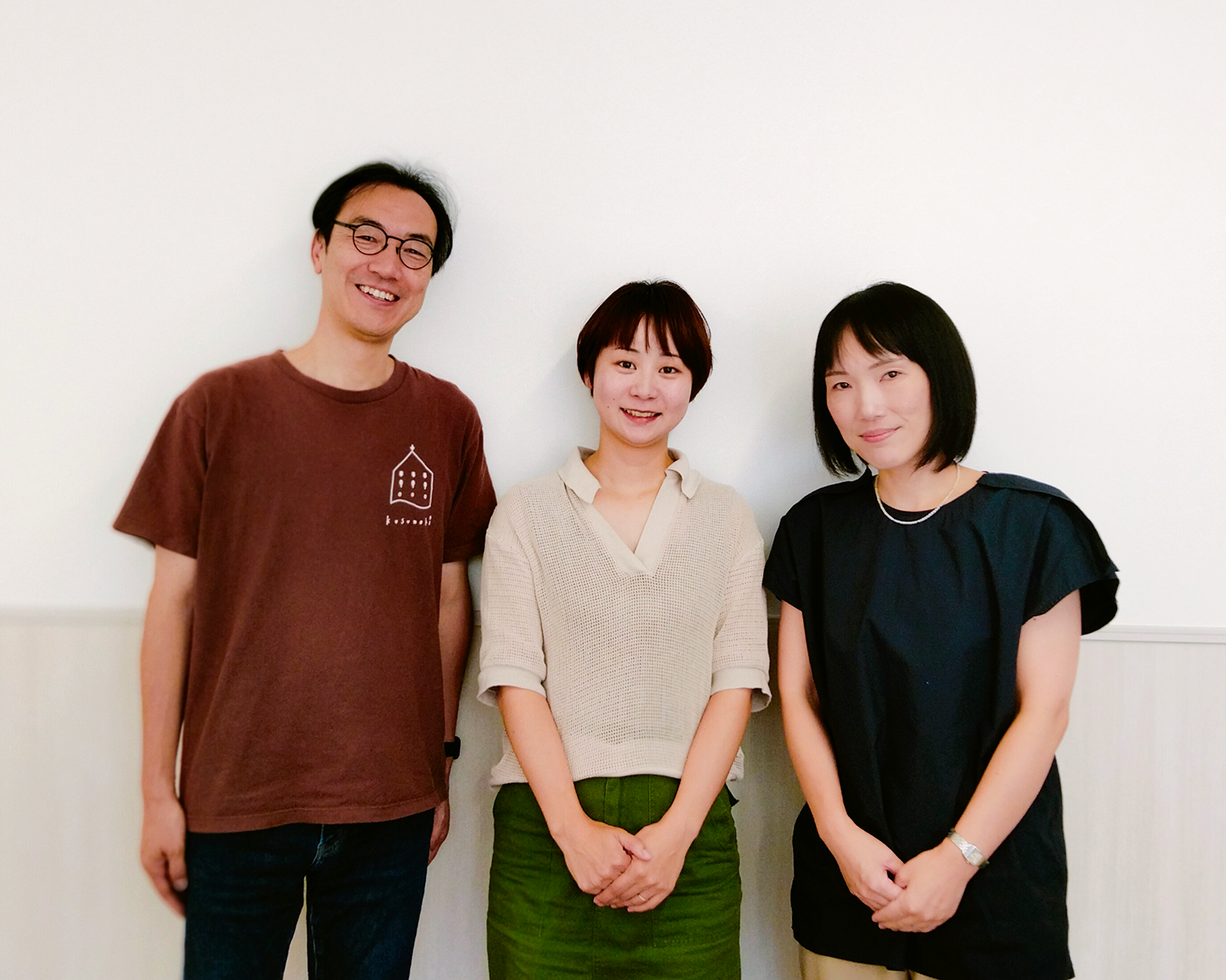
入園希望者や関係先から「くすの木ってどんな園ですか?」とよく聞かれるのですが、いつも、え~と、なんなんでしょうね~と明快に答えられない。
それが堀江大園長の悩みのひとつなんだそうです。
そこでこの度、その悩みを解消できないかと、当サイトで保護者ライターとして取材・執筆をしてくださっている石井さんと端場さんと一緒に、くすの木の魅力を探り出そうと堀江大園長と語り合っていただきました。
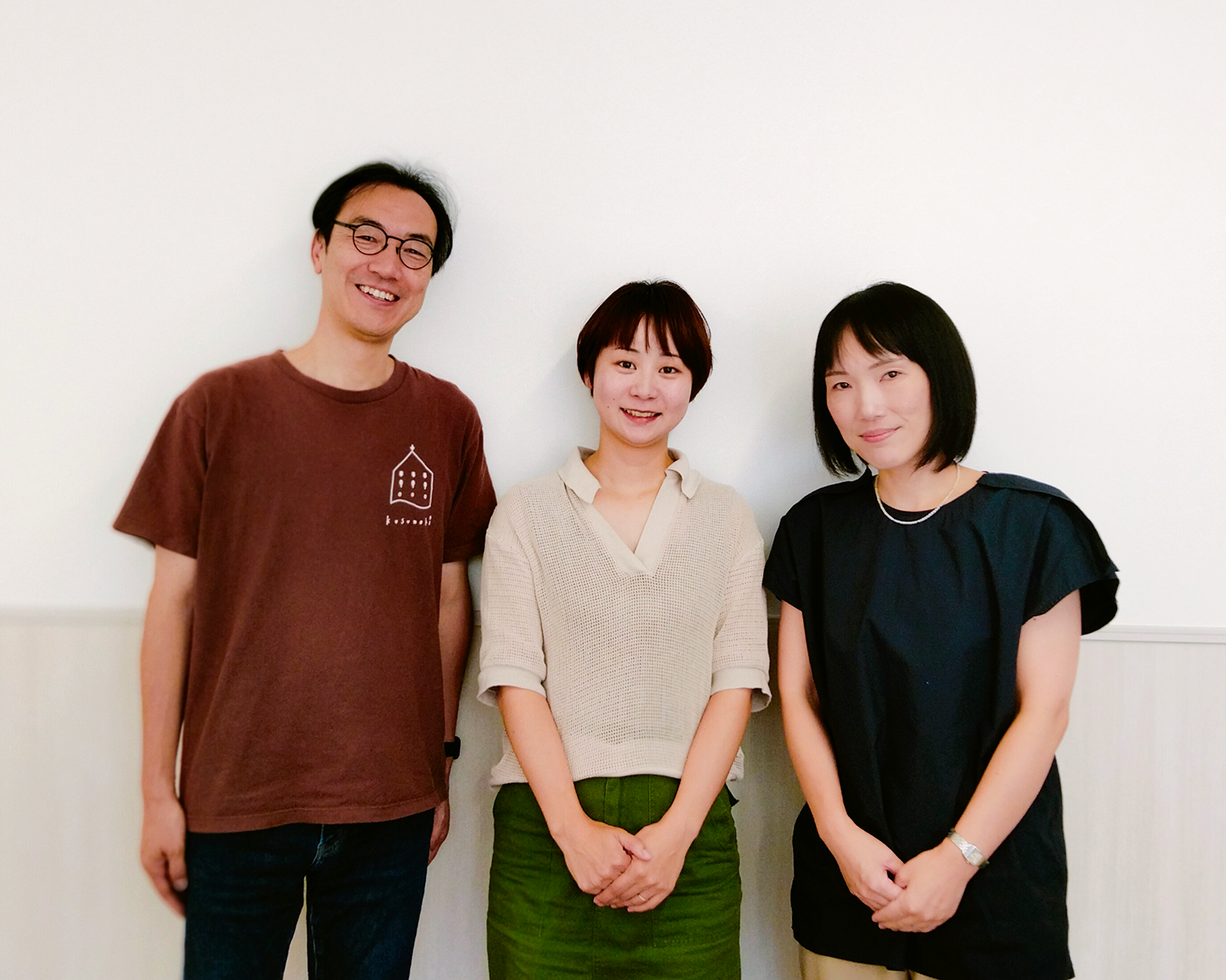
石井さんと端場さんは、お子さまが元くすの木の園児で、保護者という立場から長い間くすの木を見てくれていました。そして現在は保護者ライターとして、くすの木のスタッフや関係者を取材し内側からも見てくれています。
そんなお二人から見えているくすの木の姿に「くすの木がどんな園なのか?」のヒントがあるような気がしているのですが、まずはお二人にくすの木との出会いをお聞きしました。
-お二人のくすの木との出会いを教えてください。
石井さん
「長男が2歳のとき、私の仕事が先に決まってすぐに保育園を探したのですが決まらず焦っていました。そんな時に空きが出たといって、受け入れてくれたのがくすの木でした。」
「当時はくすの木は認可外で、事前に評判も聞かずに入園したのが始まりで、その後、次男、三男の卒園まで11年間くすの木に通い続けられました。」
端場さん
「私は引っ越しがきっかけで、あちこち近くで探していたところ、祇園園舎に入ることができました。」
くすの木は端場さんが保育園を探していた時期の前年に開園したばかりでした。そのため、端場さんも評判や予備知識もないまま4歳の息子さんの入園を決め、娘さんと合わせて6年間通われました。
くすの木の園はお家

-当時の保護者目線で印象に残っていることは何でしょう?
端場さん
「建物が保育園っぽくないところです。くすの木の前に企業内保育園に行ってたんですが、廊下からこどもたちの作品だらけで、いかにも保育園って感じでした。でもくすの木は、花が飾ってあったりしてシンプルでおしゃれ。なぜなんでしょう?」
堀江大園長
「そうですね、保育っていうよりも生活の場、こどもたちにとっての家だと考えているんですね。もし家がこどもが描いた絵ばっかりだったら落ち着きませんよね。」
端場さん
「あと、先生って呼ばずに“さん”付け。服装もよくあるエプロンではなく普段着だけどおしゃれでした。先生か保護者かわからないから、最初は戸惑いました。」
堀江大園長
「一般に先生って呼ばれてる人ってどうなのかなって思ってて、しかも経験のない保育士20代で先生って違和感ありますよね。それで自然と“さん”付けになりましたね。」
「エプロンも、おうちでずっとしている人いませんよね。家ならこどもにとって違和感でしかないと思いますよ。」
-他にも海外の玩具のことだったり、給食・おやつへのこだわりの話も出ました。
端場さん
「今日何食べたって聞いたら、こどもが『七分付ご飯』って言って、え何それって感じでした。」
堀江大園長
「乳幼児にとって食べることは生きることで、命に直結してますよね。どの親もこどもには安心・安全で手間暇かけた美味しいものを食べさせたいと思うけど、出汁をとって一食二食つくるのは面倒、大量に作るからできることってあるんですよ。」
石井さん
「おやつも本気、ほとんど手作りですよね。しかもエネルギーの高い“おにぎり”とか“うどん”や“ラーメン”なんかも。」
端場さん
「キッチンのスタッフさんに聞いたんですが、スナック菓子とかは家でも食べてるし特に土日は外食も多いので、月曜日のおやつは生活リズムを戻すためにもおにぎりとかにしているそうですね。」
石井さん
「そうですね、やっていることやちょっとした会話やふるまいにもすべて意味があるんですよ。しかも自然に。」
思いがインストールされている
-それでは、くすの木のことを取材・執筆しているライターの目線で印象に残っていることは何でしょう?
石井さん
「いろんな人にインタビューしてきましたけど、よく聞くフレーズが二つあって、ひとつは『5つで1つの園』。もうひとつは『こどもの主体性、可能性を信じてる』というのがありました。」
堀江大園長
「そうですね、わりと狭い地域に園が5つありますよね。だからこそ出来ることとしてスタッフもいろんな園を経験してもらったり、土曜日などは園児の交流もしてますね。」
石井さん
「私はくすの木が認可外の一つの園の時から知ってて、規模が大きくなってもなぜか変わらないんですよ、スタッフの印象が。違う園で初めて会うスタッフでも不思議と緊張感なく変わらず接することが出来るんです。どの園も私たちのおうちって感じで。」
堀江大園長
「こどもの主体性でいえば、今では保育の世界で当たり前になりましたが、2011年の開園準備中にイタリアのレッジョ・エミリア・アプローチという主体性を尊重する教育法でやりたいんですと言ったら、役所の窓口でそんなもの誰も知りませんよと言われました(笑)。その時、いろいろ試行錯誤して得た考え方のひとつですね。」
石井さん
「例えば木登りでも、それってこどもだけで出来るの?って思うような事も信じてやらせて乗り越えちゃうんですよ。こどものやりたい気持ちを邪魔しないっていうか、可能性を楽しんでるように見えます。」
端場さん
「それらがみなさんから感じられるし、言葉として聞きますね。」
石井さん
「大園長がこうしたいという思いが、スタッフ全員にインストールされている感じです。」
堀江大園長
「きっと私がしつこく、何度もみなさんにお伝えしているからだと思います(笑)」
端場さん
「2年目保育士さんを取材したときに、研修制度があって助かると伺いました。」
堀江大園長
「そうなんです。民間企業出身の私には、保育現場の特異性に驚きっぱなしで、現場マネージャーの不在もその一つでした。」
「そこで、各年代に分かれてもらって特有の習慣や人権意識の修正をしたり、さまざまな場面でくすの木はこう考えるということを定期的に繰り返しているんです。」
端場さん
「あと取材していて、『お互い様』という言葉もよく聞きました。仕事を休まなくちゃいけなくなった時とかいろんな場面で。」
堀江大園長
「スタッフの多くは、保育士であると同時に親でもあるんですよ。自分の子が熱出て休めない職場がくすの木っておかしくないですか。だからそんなときはお互い様だから休んでそばにいてあげてと。本人は申し訳なさもあるだろうけど長い目で見ればプラマイゼロ、お互い様なんですよ。」
-保護者としても、ライターとしても、いろんなスタッフを見てこられて、ここが魅力かなって思うことはありますか?
石井さん
「こどものお迎えの時に今日の様子をいつも教えてくれるんですが、時々こんな面白いことありましたってスマホの写真を見せてくれるんです。あ、職場にスマホってNGでしたっけ?」
堀江大園長
「公立はアウトですね。うちは全員にiPhone貸し出してます。」
石井さん
「その写真が本当に面白くて、お迎えに行くのが楽しみになりました。何よりスタッフのみなさんの方が楽しそうで。」
端場さん
「ですよね、遅く行っても疲れた表情を見たことないです!」
石井さん
「参加保育でお散歩に同行したとき、ものすごい距離を歩いたんです!帰って倒れこむくらい。これ毎日?って。こどもたちもスゴイけどスタッフのみなさんも凄い。タフじゃないとできません。」

アップデートして成長し続ける
端場さん
「週1回子どもの様子を報告してくださるドキュメントもいつも感心しています。パソコンで作られているのか内容もレイアウトもセンスよくて。」
堀江大園長
「そう、うちは入社時にスマホ、パソコン操作必修って言ってます。例えば給与振り込みで銀行に行くと1~2時間すぐ経ちますよね。パソコンなら1分とかからない。テクノロジーは時間の使い方が変わってくるんです。」
「でも苦手な方もいます。そんな時、こどもたちがお箸が苦手だから手で食べていいよっていいますか?って聞くんです。パソコンも同じですよって言うと渋々頷かれます。」
「歴史の話でいうと、織田信長は鉄砲という新技術を使って覇者になった。新しいテクノロジーを取り入れた集団が伸びるのは昔も今も同じです。その点、保育業界はとても疎いです。」
端場さん
「そういったITも研修制度も常にアップデートしているんですね。」
-くすの木の魅力を語り合ってきましたが、そろそろ時間がきました。最後にみなさん、一言お願いします。
堀江大園長
「先日、比治山大学の濱田先生から『くすの木のスタッフは輪郭がはっきりしている』と言われました。今でいえばキャラが立ってるというんでしょうか。」
「それは、保育士が“さん付け”で先生って呼べないから、先生というカテゴリーのワン・オブ・ゼムではなく、自然と一人の人として見るようになってコミュニケーションが生まれるからだと言われ、なるほどなと思いましたがいかがですか?」
端場さん
「同感です。知るようになると、思いも一人一人持っていて誰も漫然と働いていない、人としての厚みを感じます」
石井さん
「そうですね、大人たちが保育を良くしようと常に考えてますよね。その頑張ってる姿をこどもたちは毎日見ている。」
「こどもたちは学校を出るまで与えられるばっかりで、社会人になって、さあ自分で考えなさい、ってカルチャーショックだと思うんです。でも小さい時に本気の大人たちを見てるから自然に自分たちで考え出せそうです。」
堀江大園長
「悩みの解消に少し前進した気がします。今日はありがとうございました。」
石井さん、端場さん
「ありがとうございました!」
座談会を終えて
お子さんの入園時は評判も聞かずに預けられた園にもかかわらず、石井さん、端場さんが今ではくすの木の大ファンであることが、座談会からひしひしと伝わってきました。
話の中で出た比治山大学の濱田先生のお子さまもくすの木の卒園児で、濱田先生は『魅力を知りたいなら、こどもをくすの木に入れるしかない』ともおっしゃっていました。
確かに、くすの木を一言で伝えるのは難しいということが改めて分かりました。
今回のお話で何かひとつでも印象に残ったことがあれば、魅力の一端に触れていただけたのではないかと願っています。
